高校数学[総目次]
数学Ⅱ 第2章 複素数と方程式
| スライド | ノート | 演習 | |
| 1. 複素数 | |||
| 2. 2次方程式の解と判別式 | |||
| 3. 解と係数の関係 | |||
| 4. 剰余の定理・因数定理 | |||
| 5. 高次方程式 |

2. 2次方程式の解と判別式
このノートでは,方程式の係数や定数項は実数を仮定する.
2.1 解の公式
$x$ の1次方程式 $ax+b=0\ (a\neq0)$ はどんなものでも $x=-\dfrac ba$ という具合に,方程式の解を係数 $a, b$ を用いて簡単に書き表すことができた.このように方程式の係数を用いて書き表された解を解の公式という.
1次方程式 $ax+b=0$ の解の公式
\[x=-\frac ba\]
では2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ についてはどうか.1次方程式 $ax+b=0$ から見れば式自体がかなり複雑だが,1次方程式のときのように係数 $a,b,c$ の式として解を書き表すことができるのであろうか?
それを考える前にいくつかの2次方程式を実際に解いておこう.
例1 $2x^2-8=0$
変形して
\[\begin{align*}
x^2-4&=0\\[5pt]
(x+2)(x-2)&=0\\[5pt]
x&=\pm2
\end{align*}\]
例2 $x^2-4x-5=0$
変形して
\[\begin{align*}
(x+1)(x-5)&=0\\[5pt]
x&=-1,5
\end{align*}\]
これらの例では因数分解によって解を導くことができたが,別の方法によっても解を導くことができる.
例1の別解
変形して
\[\begin{align*}
x^2-4&=0\\[5pt]
x^2&=4\\[5pt]
x&=\pm2
\end{align*}\]
例2の別解
変形して
\[\begin{align*}
x^2-4x&=5\\[5pt]
(x-2)^2-4&=5\\[5pt]
(x-2)^2&=9\\[5pt]
x-2&=\pm3\\[5pt]
x&=2\pm3\\[5pt]
x&=-1,\ 5
\end{align*}\]
元の解き方に比べ,とりわけ例2では時間がかかったが,実はこの解き方の流れこそ2次方程式の解の公式を考える上でのヒントになるのだ.そこでこの解き方の流れをさらっておこう.
解法の流れ
$x^2-4x-5=0$
$\to\hspace{5mm} x^2-4x=5$ (定数項を移項)
$\to\hspace{5mm} (x-2)^2-4=5$ (左辺を平方完成)
$\to\hspace{5mm} (x-2)^2=9$ ($-4$ を移項)
$\to\hspace{5mm} x-2=\pm3$ (平方根をとる)
$\to\hspace{5mm} x=2\pm3$ ($-2$ を移項)
この流れで一般の2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解を導いてみよう.
Q. 2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解を求めよ.
A.
$ax^2+bx+c=0$
$\to x^2+\dfrac bax+\dfrac ca=0$ ($a$ で割る)
$\to x^2+\dfrac bax=-\dfrac ca$ ($\dfrac ca$ を移項)
$\to \left(x+\dfrac b{2a}\right)^2-\dfrac{b^2}{4a^2}=-\dfrac ca$ (平方完成)
$\to \left(x+\dfrac b{2a}\right)^2=\dfrac {b^2-4ac}{4a^2}$ ($-\dfrac{b^2}{4a^2}$ を移項)
$\to x+\dfrac b{2a}=\pm\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (平方根をとる)
$\to \underline{\boldsymbol{x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}}$ ($\dfrac b{2a}$ を移項)
重要な補足
特に1次の係数が $2b’$ のとき,すなわち $ax^2+2b\,’x+c=0$ のとき,解の公式を使って解を計算すると
\[\begin{align*} x&=\frac{-2b\,’\pm\sqrt{(2b\,’\,)^2-4ac}}{2a}\\[5pt] &=\frac{-2b\,’\pm2\sqrt{{b\,’\,}^2-ac}}{2a}\\[5pt] &=\underline{\boldsymbol{\frac{-b\,’\pm\sqrt{{b\,’\,}^2-ac}}{a}}} \end{align*}\]
となって計算が大幅に省力化できる.
2次方程式の解の公式
2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解は,
\[x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\]
また,$ax^2+2b\,’x+c=0$ のときは,
\[x=\frac{-b\,’\pm\sqrt{{b\,’\,}^2-ac}}a\]
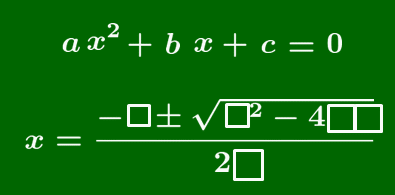
例題 次の2次方程式を解け.
(1) $x^2+5x-2=0$
(2) $3x^2-x+1=0$
(3) $x^2+6x-3=0$
こたえ
(1)
解答例を表示する
\[\begin{align*}
x&=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\cdot1\cdot(-2)}}{2\cdot1}\\[5pt]
&=\underline{\boldsymbol{\frac{-5\pm\sqrt{33}}2}}
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
x&=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\cdot1\cdot(-2)}}{2\cdot1}\\[5pt]
&=\underline{\boldsymbol{\frac{-5\pm\sqrt{33}}2}}
\end{align*}\]
(2)
解答例を表示する
\[\begin{align*}
x&=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-4\cdot3\cdot1}}{2\cdot3}\\[5pt]
&=\frac{1\pm\sqrt{-11}}6\\[5pt]
&=\underline{\boldsymbol{\frac{1\pm\sqrt{11}\,i}6}}
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
x&=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-4\cdot3\cdot1}}{2\cdot3}\\[5pt]
&=\frac{1\pm\sqrt{-11}}6\\[5pt]
&=\underline{\boldsymbol{\frac{1\pm\sqrt{11}\,i}6}}
\end{align*}\]
(3)
解答例を表示する
\[\begin{align*}
x&=\frac{-3\pm\sqrt{3^2-1\cdot(-3)}}1\\[5pt]
&=-3\pm\sqrt{12}\\[5pt]
&=\underline{\boldsymbol{-3\pm2\sqrt3}}
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
x&=\frac{-3\pm\sqrt{3^2-1\cdot(-3)}}1\\[5pt]
&=-3\pm\sqrt{12}\\[5pt]
&=\underline{\boldsymbol{-3\pm2\sqrt3}}
\end{align*}\]

2.2 判別式
次の3つの2次方程式を,解の公式を用いて解いてみよう.

